コラムCOLUMN
極端な考え方の罠:リーダーが陥りやすい二者択一の思考を超えて
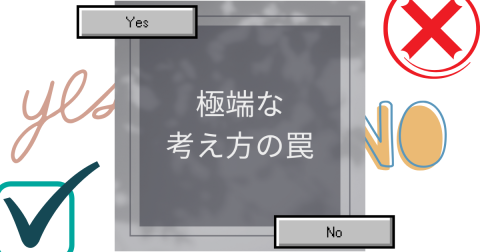
極端な考え方の罠:リーダーが陥りやすい二者択一の思考を超えて
私たちは日常生活や仕事の中で、何かを決断するときに
「白か黒か」「やるかやらないか」といった二者択一の考え方をしがちです。
このような思考は、一見シンプルでわかりやすい選択肢を提供してくれるように見えますが、
実は大きな罠を孕んでいます。
特にリーダーシップにおいて、
極端な思考はチームやプロジェクトに深刻な影響を与える可能性があります。
この記事では、二者択一の思考がどのような問題を引き起こすのか、
そしてそれを超えるための方法について考えていきます。
二者択一の思考が引き起こす罠
人間は無意識のうちに物事を「どちらか一方」として捉える傾向があります。
例えば、職場で次のような会話が交わされることがあります。
- 「やる気がないなら辞めたら?」
- 「やる気があるんだったら徹底的にやろうよ!」
これらの発言は、シンプルで断定的に見える一方で、極端な思考に基づいています。
こうした二者択一の考え方には、以下のような問題点が潜んでいます。
1. 反作用のリスク
極端な行動を選ぶと、その反動として予期しない問題が発生することがあります。
たとえば、「やる気がないなら辞めさせる」という選択肢を取った結果、
人手不足で業務が回らなくなることが考えられます。
一方で、「徹底的にやる」と決めて無理を重ねれば、
メンバーが体調を崩してしまう可能性もでてきます。
2. 柔軟性の欠如
二者択一の思考は、中間の選択肢や代替案を見逃してしまう傾向があり、
その結果、問題解決のための柔軟なアプローチが取れなくなります。
3. チームのモチベーション低下
「白か黒か」という極端な判断は、チームメンバーにプレッシャーを与えたり、
不安感を抱かせたりすることがあります。
これが長期的に続くと、メンバーのモチベーションや
士気に悪影響を及ぼす可能性があるのです。
自分のバランスの支点を見つける
では、このような極端な考え方を回避し、
より効果的な判断をするためにはどうすれば良いのでしょうか?
その答えは、「自分なりのバランスの支点を見つけること」です。
真ん中を取るのではなく、自分の価値観を基準に
バランスを取るというと、「ちょうど真ん中を選べば良い」と考えがちですが、
それだけでは不十分です。
重要なのは、自分自身の価値観に基づいてどちらに重心を置くかを決めることです。
ただし、その際にも極端に偏ることなく、
反対側の視点や可能性を完全に排除しないことが大切です。
極端な思考を超える具体例
以下のような具体的な考え方が、極端な二者択一の罠を回避する助けとなります。
1. やる気の問題に対するアプローチ
- 極端な選択肢:「やる気がないなら辞める」「徹底的にやる」
- バランスの支点:「やる気に左右されない仕組みを考える」「効率的に取り組める方法を模索する」
たとえば、やる気のないメンバーに対しては、
日々のモチベーションを高める仕組みやサポート体制を整えることで、
パフォーマンスの向上が期待できます。
2. 仕事量の調整
- 極端な選択肢:「何もやらない」「全部やる」
- バランスの支点:「優先順位をつけて重要なタスクに集中する」
すべてを完璧にこなそうとすると、疲弊してしまいます。優先順位をつけ、
効率的にタスクを処理することで、結果として成果が高まることもあります。
自分自身を振り返る時間を持つ
極端な考え方を回避し、バランスの取れた選択をするためには、
自分自身を振り返る時間を持つことが不可欠です。
具体的には、一日の終わりに以下のような質問を自分に投げかけてみましょう。
- 今日の判断はどのように行ったか?
- 極端な考え方に陥っていなかったか?
- 他の選択肢や視点があったのではないか?
たった10分間、自分を振り返る時間を設けることで、
考えのクセやパターンを見つけることができます。
これは長期的な成長の大きな一歩となるのです。
まとめ:柔軟な視点を持つリーダーを目指して
極端な二者択一の思考は、一見簡単に問題を解決しているように見えますが、
その裏には多くのリスクが潜んでいます。
自分なりのバランスの支点を見つけ、柔軟な判断ができるリーダーになることが、
チームやプロジェクトの成功に繋がります。
まずは、自分自身を振り返る時間を持つことから始めてみましょう。
それが、極端な考え方の罠を超え、より良い選択をするための第一歩です。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。

質問型コミュニケーション協会代表理事
30代の頃、激務に追われ自身の心身のバランスを崩しうつ病で休職。
その頃にコーチングに出会い人生が大きく変化。
累計発行部数20万部の質問型営業開発者青木毅からコーチングや質問型営業を習いその後、15年10,000時間に及び、相手の深い価値観を引き出し寄り添うコーチングを行う。
中小企業社長様から中学生まで多種多様な方のサポートをしてきた経験から質問型コミュニケーションを法務省等の自治体、および製造業・士業・保険会社・介護・製薬会社・美容業等へと広める活動をしている。好きなものは奥さんとの神社巡りと歌うこと。実は過去に音楽活動をしていました。
