コラムCOLUMN
気配り上手な人が“やりがち”な落とし穴
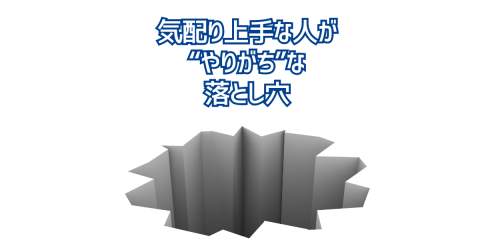
こんにちは!
安井です。今日はちょっと面白いテーマを持ってきました。
「長所と短所って、実は同じものなんじゃない?」という話、聞いたことありませんか?
“表裏一体”ってやつですね。
この考え方、自己分析とか就活の面接なんかでよく聞く話なんですが、言われてみれば確かに…と、膝を打ちたくなる一方で、「それで何が変わるの?」と、もやっとする部分もあるんです。
今日はそんな“長所と短所の裏表理論”について、ちょっと突っ込んで考えてみようと思います。
目次
- 【1】「長所は短所の裏返し」って本当?
- 【2】一般論では見逃されがちなこと
- 【3】“直す”べきなのか、“活かす”べきなのか?
- 【4】「付き合い方」という視点の大切さ
- 【5】解決のヒントは「問いかけ」
- 【6】「バランス」を取り戻すという発想
- 【7】というわけで:短所を嫌わず、うまく扱おう
【1】「長所は短所の裏返し」って本当?
よく言われるのはこんな感じです。
-
「慎重な人」は「優柔不断」と言われることがある
-
「決断力がある人」は「せっかち」とも見られる
-
「空気が読める人」は「自己主張が苦手」となることも
つまり、性格や特性には“光と影”がセットになっているという考え方ですね。
これって確かに一理あるんですよ。
誰かの強みを見つけようとすると、たいていその強みには“やりすぎた場合”のリスクがくっついてきます。たとえば「完璧主義」。これ、ある程度までは素晴らしいこだわりなんですが、行き過ぎると「時間がかかりすぎる」「人を巻き込めない」みたいな短所に変わるんですよね。
【2】一般論では見逃されがちなこと
ただ、この「裏返し」理論、ちょっとした落とし穴があると思うんです。
というのも、「全部裏返しでOKなら、短所は気にしなくていいよね!」って話になると、それはそれで現実的じゃないんですよ。
実際の仕事や人間関係では、「いやいや、それ本気で困るんだよなあ…」という短所が、ちゃんと問題になることがあります。たとえば、「慎重すぎて決断が遅い」とか、「空気を読みすぎて、会議で一言も喋らない」とか。
つまり、表裏一体なのは理解できるけど、「それでどう向き合えばいいのか?」が、抜け落ちやすいのです。
【3】“直す”べきなのか、“活かす”べきなのか?
ここで、ありがちな悩みが出てきます。
「短所って、直すべきなんでしょうか?」
うーん。これ、めちゃくちゃよく聞かれます。でも、正直に言うと「全部直すのは現実的じゃない」と思っています。
たとえば、「感性が豊かすぎて相手の気持ちばかり気にしてしまう」という人。これを「もっとドライになれ」と言っても、なかなか難しいですよね。なにせ、その“感性”がその人の魅力であり、武器でもあるからです。
とはいえ、そのまま感情に流されて行動できなくなってしまったら、成果にはつながりません。
そこで大事なのが、「特性との付き合い方」です。
【4】「付き合い方」という視点の大切さ
私がサポートしている方々の中には、「気配り上手」「感受性豊か」「共感力が高い」といった、いわゆる“優しさのかたまり”みたいな方が多くいます。
でも、こういう方に限って──
「何を目的にしていたか」がふっと抜け落ちてしまうことがよくあるんです。
たとえば、会議の場で、
「みんながどう感じてるか」に気を取られすぎて、
「今の議題って何だったっけ?」と自分を見失ったり。
これって“能力不足”ではなく、むしろ“感性が高いがゆえの現象”なんですよね。
【5】解決のヒントは「問いかけ」
では、どうしたらいいのでしょうか?
私はこう考えています。
特性を変えるのではなく、「使い方」を整える。
そのために役立つのが、「自分への問いかけ」です。
たとえば、こんな問いを自分に投げてみてください。
-
今、この行動は何のためにやっているんだっけ?
-
この仕事のゴールって何?
-
相手にとっての価値は何だろう?
-
成果って、どうなったら「出た」と言える?
こうした問いをセットにしておくと、感性や優しさが“迷走”しづらくなります。
言い換えると、「優しさが成果につながる設計」ができるんです。
【6】「バランス」を取り戻すという発想
とはいえ、「じゃあ常に問いを持ち続けましょう!」というのも、ちょっと息苦しいですよね。
だからこそ、時々でいいんです。
気づいた時に「自分に問いかけるクセ」をつける。それだけで、自分の強みが“強みのまま”活かされるようになります。
つまり、短所を消す必要はありません。
むしろ「これは長所の過剰バージョンだ」と気づいてあげることが、冷静なマネジメントにつながります。
【7】というわけで:短所を嫌わず、うまく扱おう
最後にもう一度、まとめておきます。
-
長所と短所は、確かに裏表。
-
でも、裏返しだからといって無視していいわけではない。
-
特性は変えずに、「使い方」を整えるほうが現実的。
-
問いかけを自分にセットして、感性と成果のバランスを取ろう。
私たちはみんな、ちょっとずつ偏っていて、だからこそ面白いんだと思います。
その“偏り”を「どう付き合うか」が、人生や仕事をうまく進める鍵なのかもしれません。
「短所を直そう」と頑張りすぎて疲れているあなたへ。
まずは、自分の特性を“否定”ではなく、“マネジメント”してみることから始めてみてくださいね。
【8】「気配り×成果」を実現するサポート、始まっています
現在、期間&人数限定で
【個人向け・特別セールスコンサルティング】を受付中です。
あなたの気配りと感性に、
質問型コミュニケーションを掛け合わせることで、
「自分らしさ」を活かしながら成果を出すための、
\こんな方へおすすめです/
![]() もっと売上を伸ばしたい
もっと売上を伸ばしたい
![]() 今のやり方に限界を感じている
今のやり方に限界を感じている
![]() お客様にもっと信頼され、選ばれるようになりたい
お客様にもっと信頼され、選ばれるようになりたい
![]() 自信を持って、成果を出したい
自信を持って、成果を出したい
![]() 結果、売上をもっとあげたい
結果、売上をもっとあげたい
「あなたの気配りと感性に、質問型コミュニケーションを。
お客様に選ばれ、仲間とともに成果を築く未来へ。」
また、法人経営者の方には、
「気配りと感性を活かし、質問型コミュニケーションで磨く。
お客様に選ばれ、仲間と成果を築く人財へ。」
そんな世界を一緒に実現していきたいと思っています。
![]() 【ご案内ページはこちら】
【ご案内ページはこちら】
https://shitsumongata.com/
最後までお読みいただき、ありがとうございました!
それでは、良い一日を。
<新時代のリーダーに必要な「人を活かし、伸ばす」
次回は、6月14日(土)10:00~11:30
![]() 売上が伸びない、安定しない
売上が伸びない、安定しない
![]() 優秀な人材の確保が難しい、すぐに離職してしまう
優秀な人材の確保が難しい、すぐに離職してしまう
![]() メンバーが主体的に動かない、指示待ちの状態が続く
メンバーが主体的に動かない、指示待ちの状態が続く
![]() 相談できる相手がいない、経営やリーダー業務が孤独に感じる
相談できる相手がいない、経営やリーダー業務が孤独に感じる
![]() チームに一体感がなく、成果がなかなか上がらない
チームに一体感がなく、成果がなかなか上がらない
そんな方はぜひご参加ください。
![]() セミナー参加者には 「1on1実践ワークシート」 をプレゼント!
セミナー参加者には 「1on1実践ワークシート」 をプレゼント!
![]() 個別相談セッション(希望者限定)
個別相談セッション(希望者限定)
<お客様との距離が自然と深まる、質問型コミュニケーションセミナー>
次回は、5月31日(土)10:00~12:00
お客様と話していて、こんな風に感じたことはありませんか?
- 話は盛り上がるのに、なぜかその後につながらない
- 信頼関係を築きたいのに、何をどう聞いていいかわからない
- リピートや紹介がもっと増えたらいいのに…
そんな“あと一歩”の壁を超える鍵が、「質問のしかた」にあります。
質問型コミュニケーションとは、 相手の本音や想いを自然に引き出し、信頼関係を築きながら対話を深めていく技術。
この体験セミナーでは、そのエッセンスを120分で体感していただきます。
<質問型コミュニケーション協会の講座情報!>
新年度がスタート!このタイミングで
「今年こそ、関わり方を見直したい」
「チームの力を底上げしたい」
と思っている方へ、目的別の講座をご用意しています。
「自然と選ばれ、関係性が深まる“質問のコツ”は?」
![]() 質問型コミュニケーションセミナー
質問型コミュニケーションセミナー
「売り込まずに選ばれる自分になりたい」
![]() 質問型コミュニケーション実践マスター講座
質問型コミュニケーション実践マスター講座
質問型の基礎をしっかり身につける人気講座です。
「チームや人材育成に活かしたい」という方には
![]() 新時代のリーダーに必要な「人を活かし、伸ばす」
新時代のリーダーに必要な「人を活かし、伸ばす」
![]() 新質問型リーダーシップ講座
新質問型リーダーシップ講座
![]() チームビルディング力養成講座(
チームビルディング力養成講座(
リーダーとして求められる“対話の技術”を、構造から学べます。
また、「自分自身の軸を整えたい」「
という方には、
![]() セルフコミュニケーション講座
セルフコミュニケーション講座
「気になるけど、どれが自分に合ってるか分からない…」
そんな方は、お問い合わせよりご連絡ください。
あなたにぴったりの学び方をご案内します。
こちらのコラムに興味を持たれましたら、
メルマガの登録がオススメです👇
▶質問型コミュニケーション協会メルマガ 登録◀
登録おまちしてます!
spotifyにて、音声配信をしています。

▶Leaders-Lounge◀
リーダーやこれからリーダーになる方がホッとひと息つける、寄り添い型サポート番組です。
日々の悩みや葛藤を一緒に考えながら、
具体的なコミュニケーションのコツやリーダーシップのヒントをお届けします。
また、メンバー視点の『リーダーってどう思ってるの?』というリアルな疑問にも答え、
リーダーもメンバーも前向きに進める架け橋となる内容を目指しています。
作業をしながら、仕事をしながら、家事をしながら、お茶でも飲みながら…
ぜひ、お聴きください!
